�@�@�@�@�@1415m���u�[���}�b�^�[�z�����v(1415.6m)
 |
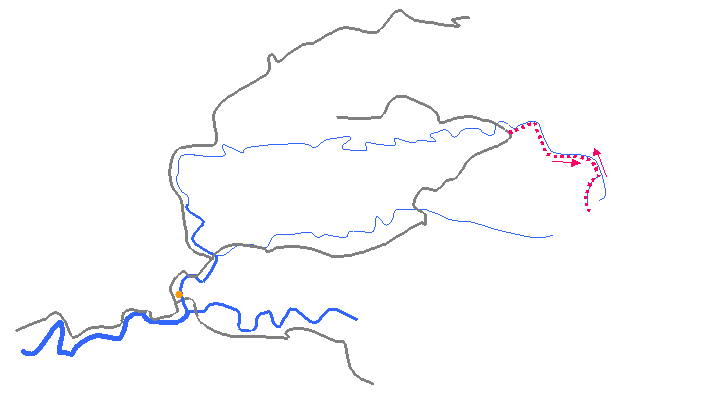 |
|
�P/25000�n�`�}�u���ʊx�v�u�[���x�v�u��t�ʊx�v�u��m��x�v
 |
| ���߂Ėڂɂ���A1415m�������� |
 |
| �ނ�5��ڂňꏏ�ɓo�� |
 |
| �Ԏ~�߁A���t��(545m)�܂ŎԂœ���邱�Ƃ͂߂��炵�� |
 |
| 730m��҂������r���̃X�m�[�u���b�W |
 |
| 730m��Ҏ�O�̃S���W�� |
 |
| �U��Ԃ�ƍ��G�V���[�p���x��E�G���ʊx�������� |
�@�����g�[���}�b�^�[�z�����h�Ƃ����A1415����̈��̂��͂��߂Ēm�����̂� ���a56�N�̍��ŁA�u�D�y���猩����R�v (�k��}�����s��)�Ƃ����{�����X�ŗ����ǂ݂������������B���ʊx�Ɨ[���x�̂قڒ��Ԃɉf��s��������p�ɂ́A���₪��ɂ�������������ꂽ���A�ē��̖������̎R��o�邱�ƂȂǁA�����̎��ɂ͂ƂĂ��l�����Ȃ������B
�@�[�����ʂ̉s��������R�݂͂�� �g���ʊx�h�ɂ���Ă��܂��X��������B����1415����ƒʏ́u���x�v�����ɊԈ����悤�ŁA���R�Ƃ��ć@���̎R��ŃK�C�h�u�b�N�ɍڂ��Ă����ʓI�ȎR�͈��ʊx�E�[���x�̂Q�R���炢�ł��邱�ƁB�A�悭�ʐ^�ł݂鈰�ʊx�͋�������̂��̂������A���̎p�͉s������Ă��邱�ƂȂǂ���������B
���݂������Ă���ƃS���W���ƂȂ��Ă��āA������730m��҂ł���B�����̓S���W����O���獶�݂��������̂���ʓI�Ȃ̂��A��ɖ߂邠����͓��ݐՂ炵����ԂɂȂ��Ă���B���̐�͐��ʂ����蕽�}�ȑƂȂ邪�A���x���グ�čs���B800���t�߂Ő��͌͂��B1000m���炢�܂ł͊�����肵�Ă��ĕ����₷�����A1000m���z����ƌX�������Ă��āA����s����ƂȂ�A�㑱�ւ̗��ɑ��钍�ӂ��K�v�ł���B1100m�t�߂���͏���(�����͂Ȃ�)�̘A���ƂȂ�C�������Ȃ��B�U��Ԃ�ƃV���[�p���x���_�ԂɌ����B�ꂵ�A���ɐ��n��̐��E���̂��̂ł���B1190���t�߂ŏ��z������ȏ���(���)�������B���̍�����J���~��o���BC1�Ƀn���}�[��u���Ă������ߎx�_�����Ȃ��ŁA����ȏ�i�ݑ����邱�Ƃ͊댯�Ɣ��f�A���̓��͂����܂łƂ���BC1�ɖ߂������ɂ͉J�r�����Ȃ苭�܂�A�ѓ��̏�Ԃ��S�z�ɂȂ�B���[�_�[�̔��f�Ńe���g��P���A�Ԏ~�߂܂Ŗ߂��ӗl�q�����邱�Ƃ����肷��B�����͋�(545��)����̍ăX�^�[�g�ƂȂ�B
 |
 |
| 1415��(�[���}�b�^�[�z����)����ɂ� | 1415m������̓O�p�_�u�V���v�ƃT�b�|�������x�� |
����(8/4)�͉J���~���߁A�܂��̂Ȃ�5�����ōs�����J�n����B1100m�t�߂���͔����ɓ����邪�A������M�����ƂȂ�B�A�H�̃��[�g�t�@�C���f�B���O�̓�����l���A�v���X�ɐԕz�����ѐi��ōs���B���̕ӂ�̒n�`�́A���~���[�g���ԈႦ��Ɠ������ɉ��R�o���Ȃ��Ȃ�댯�����l������B�R�e���}�s�ł��邽�ߔ�����ɂ͏��X��ǂ�����邪�A���𗘗p���ĉ��Ƃ������o��(����͂��ׂČ������~)�B
�M�˓������Q���ԂŒ���̌�(1380m)�ɔ�яo���B�����̗Ő�����M���ɂ̓i�^�̐Ղ��c���Ă����B���߂Ē������ڂɂ��邪�A�i�s�����ɂ͒���܂œr��邱�ƂȂ������������Ă���A�����ɂƂ��Ă̏��o�����m�M����B��30���A�Ō�̋}�Ζʂ��o��ƁA�ӊO�ɍL�����R�Ȓ���ɔ�яo�����B�i�s��������̑����ɂ͓����1415m��O�p�_������A5�x�ڂ̒���Łu�[���}�b�^�[�z�����v�s�[�N�𗎂Ƃ�����т����ݏグ�Ă���B�ŏ��̌v�悩�炸���Ƌ��ɂ��̃s�[�N��ڎw���Ă������Ԃ��A�O�p�_��G��Ȃ�����ł���p�����Ɉ�ۓI�������B(2002.8.4)
�y�Q�l�R�[�X�^�C���z(8/3)
�y�����o�[�zL.hachiya�ASL.saijyo�Am.hachiya�A�`����2�Aisido
�ܔN���1415m�u�[���}�b�^�[�z�����v�̎R�s��