月見山(660.8m)
|
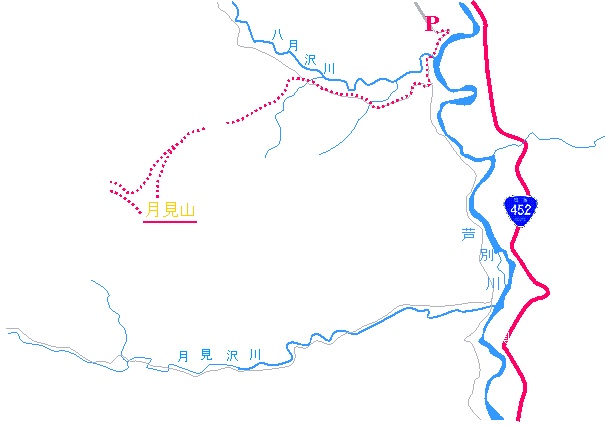 |
1/25000地形図「奥芦別」
 |
| 除雪終点(咲別林道入口)に車を停める |
 |
| 林道に続く先行者のトレースとシカの足跡 |
 |
| 途中に現われたキタキツネ、身ごもっているのだろうか・・・ |
月見山をWeb上で調べてみると第一に神戸市須磨区の月見山という地名が現われる。当然のことだが「月見」に関しての言い伝えがある場所だ。この須磨区の月見山だが、現在は山陽電気鉄道の駅名で、百人一首に登場する平安時代の歌人・在原行平が下向した折に秋月を眺めた場所ということに由来しているそうである。また、高知県にも月見山という小さな山があるが、こちらも土御門上皇ゆかりの地とのこと。さて、今回登った月見山であるが、大正時代に設置された三等三角点の点名がそのまま山名となっているようだ。明らかに和名であり、アイヌ語地名ではない。月見山の名が点名となった経緯は判らないが、現地から見る月が素晴らしかったのか、当時の関係者が故郷を思い出して命名したものなのか、あるいは遠いこの地に来て自分を歴史上の高貴な人物になぞらえたものなのか、その何れかであろうと思われる。この地域の山名に実際に内地(本州・四国・九州)にある山の名が多いことを考えれば前述の地名が絡んでいても不思議はない。いずれにしても三角点設置の際の行きがかり上の命名であろう。
 |
| 月見山最高地点(672m地点)はどこにでもある平凡な尾根上 |
500m程度の山でもあり、札幌発日帰りで充分と現地へ向う。アプローチは辺毛山や番ノ沢山と同じ八月の沢林道からである。道道分岐を過ぎ、途中で対岸へ渡る道路もあるが、どこまで除雪されているかは判らず、川岸大橋まで行くのが遠回りではあるが間違いないところだ。昨年の夏に訪れた八月の沢林道は伐採作業が行われている感じだったので除雪も期待したが、最終人家を過ぎた辺りまでであった。林道は下りから始まる。帰路を考えると少し億劫であるが、私のメンテナンスしていないスキーであればシールなしの状態でも大丈夫だろう。下りきったところで芦別川対岸からの道路と合流する。車の轍のようにも見えるが良く見ればシカの足跡、不思議なのは昨日と思われるスキーのトレースがここから始まっていることだ。この時期であれば、辺毛山までは遠く、とても日帰りで登れる距離ではない。となれば、目的は我々と同じ月見山だろう。この時期この山に取り付くことが想像できる人物は北野のSさんかKo玉氏くらいかな、などと軽い会話を交わしながら林道に続くトレースを使わせてもらう。トレースの主は所々で休憩と偵察を繰り返しているのか、途中途中であちこちに向かっている。だが、我々には我々の良いと思えるルートがあり、水線のある小沢を渡ってすぐの斜面でトレースから離れることにする。
北側の斜面は等高線こそ緩いが小沢が入組んでいて地形図から読み取れる平易な印象とは少し違うようだ。広い雪面は疎林帯となっていて少しずつ標高を上げて行く。それにしても付近にはシカの形跡が多く見られ、寝床と思われるところも何度か通過する。380m標高点付近を通過、前方に明瞭な尾根地形が現われる。手前の植林帯の中を集材路が真っ直ぐに上へと向かっている。ふと見るとキタキツネが一匹、こちらを警戒するように見ているが逃げようとはしない。病気で弱っているようにも見えるが、今のこの時期を考えればきっと身ごもっているのだろう。さすがに近づくと植林帯の中へと身を隠し、こちらの動きをじっと見ていた。招かざる客と映ったのであろう。
 |
 |
| 狭くて頂上らしい三角点ピーク(本峰) | 月見山頂上にて |
 |
 |
| 頂上からイルムケップ山方面を望む | 下りはそれなりにスキーが楽しめる |
集材路を上って行くと正面に尾根の斜面が現れる。ここは末端付近から尾根上へと回り込み、みるみる標高を上げて行く。尾根は痩せていてやっと登山らしくなるが、直ぐに高みとなる。こんな近くに頂上があるはずはなく、地形図を見るとコンタでは表現されていないコブのようである。せっかく登ったのに直ぐに大きく下らなければならないようだ。ただし、コンタで考えれば10m未満の下りといったところだ。月見山の頂上は標高660mだが、0.7kmほど北西側には10mほど高い672mのピークがあり、山域を広げて考えればこちらが頂上ということになる。また、さらに拡大した場合、北西側にはもっと高いコンタ700mのピークもあるが、ここまでエリアを広げてしまってはもはや月見山とは言えないだろう。とりあえずは672m標高点を踏んでから三角点ピークへ向かうことにする。
尾根は回り込むように両ピークを繋ぐ稜線の斜面へと消え、北西風のために波打ったような凹凸状の雪面を登り詰めて672m標高点へと到着する。やはり600m程度の山で、樹林のために展望はいまひとつである。疎林の隙間からイルムケップ山が見えるが、それ以外の遠い山々は雪雲に霞んで形が特定できない。おそらく比較的近い烏帽子岳や金剛岳は見えているのであろうが、木々が邪魔して山座同定の気分ではない。意外と費やした時間に、すぐに三角点ピークへと向うことにする。直線距離にして700m、藪漕ぎとなる夏であればそれなりに時間を費やすところだろう。藪の妙味は夏ならではのものだが、冬の積雪での短絡はやはり凄く得をした気分にさせる。標高こそ低いが、途中から見る本峰は競りあがっていてなかなかである。
見た目ほどではないが、最後は傾斜のある斜面を登り詰めて狭い頂上となる。やはりこちらの方が頂上にふさわしい。樹林が眺望を邪魔してはいるが、角度によってはすっきりとした眺望も得られる。真っ白な美唄山が半分だけ見え、イルムケップ山も先ほどよりはすっきりと見えている。予想に反してトレースが見当たらない。彼らは八月の沢林道からどこへ向かったのだろうか。ひょっとして、辺毛山を越え美唄山までの縦走に出かけたのかもしれない。やはりこの山のみに食指を動かす登山者は少ないということだ。地形図を出してさっそく下りのルートを考える。総じて傾斜の緩い斜面ではあるが、小沢へ入ってしまっては意外と面倒である。登ってきたルートの尾根取付き付近を目指してトラバース気味に下るのが、考えうる一番リスクが少ない選択といえそうだ。
月見山、頂上から中秋の名月としたいところだが、秋のその時期では深い藪の中となるだろう。やはり麓からススキの穂を通して眺めるこの山と名月が良いようである。歌才があれば在原行平さながらの一句できそうな山名である。スキー底の雪の団子からお月見を連想するメンバーもいたようだが、私にとっては風情を十分に感じさせる月見山であった。(2010.2.21)
■LuckyさんのBlog「月見山」へ
【参考コースタイム】
除雪終点(咲別林道入口) P 9:30 → 672mピーク 12:20 → 月見山頂上 13:00 、〃発 13:30 → 除雪終点(咲別林道入口) P 15:00
(登り3時間30分、下り1時間30分)
【メンバー】Luckyさん、saijyo、チロロ2、チロロ3(旧姓naga)