小平蘂岳(960.5m)
|
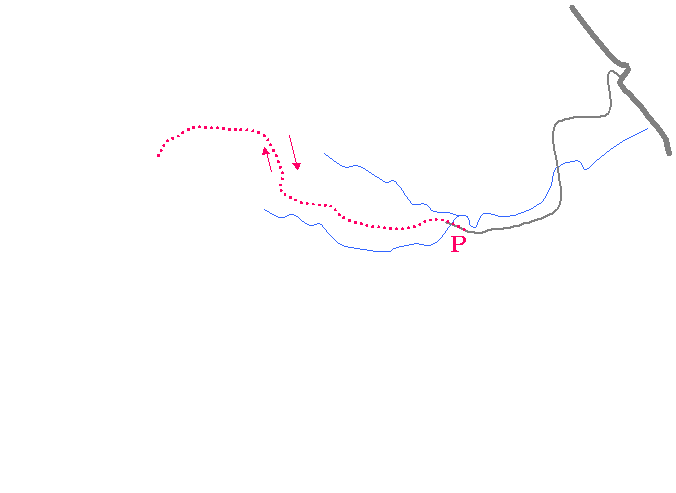
|
1/25000地形図 「三頭山」
 |
| 林道終点の駐車スペース |
 |
| 十三線沿いの林道を進む |
「オビラシベ」の名はアイヌ語で「オビラ=河口に・崖・がある」と「シベ=峠」に由来する。小平蘂村は昭和23年に現在の小平町となったが、二級河川「小平蘂川」にはその名が残った。「小平蘂岳」はこの川の源流の山である。この山の南方にも「小平蘂山」という同名の山があり、以前の地形図には単に「小平蘂」と記されていた。ここもやはり小平蘂川の源流であるが、奥深さでは「小平蘂岳」の方に分がある。幌加内側から見ると目と鼻の先であるが、小平側からは奥深い遼かな山である。
 |
| 尾根に取り付くと本峰が迫ってくる |
 |
| .565m付近はよい展望台となっている |
アプローチは幌加内町の国道275号線を進み、政和温泉「ルオント」を過ぎ、政和の市街を越え、約5km進んだ新富地区が林道入口である。林道は十三線川沿いについており、二股付近の取水施設まで除雪されていた。除雪終了地点に車を置く。左股に掛かる橋を渡り、直ぐに尾根に取り付く。.360mを右に巻き.565mまで約1時間である。.565mは平野がよく見渡せる絶好の展望台で、登山道があれば、間違いなく「見返り台」といった名称が付くことだろう。ここから斜面も広くなり、左手に小平蘂岳を見ながら、大きく右に回り込む。標高650m付近から尾根は再び狭まり、主稜線へと続いている。920mピークは巻いて、コルへ直接飛び出すことにする。新雪が積もっていれば、こんな大胆なトラバースはとても出来ない。
天塩山地の主稜線は付近(特に小平町側)に高い山が無いためか、とても900mでは味わえない雄大さがある。今年は例年にない黄砂の影響で、山全体がセピア色であった。キタキツネが一頭、こちらを怪しげに窺いながらピークの方向へ一目散に逃げて行った。ここのキツネにとって登山者は、めったに見ることのない奇妙な存在なのだろう。小平蘂岳のピークには、登山者がよくピークに付ける赤布が無かったので、一つ付けることにする。三角点も探してはみたが、まだ雪の下なのか見つけることは出来なかった。
天塩山地の中で1000mを越えるピークは、北のピッシリ山と南の三頭山だけで、小平蘂岳は第3の高峰である。ただ、すぐ隣の主稜線上のピークは標高が990m〜1000mあり、東側が険しく切れ落ちている姿はなかなか風格があり、こちらのほうが小平蘂岳の名に相応しい気がする。
帰路は登ってきたルートを下る。帰りの車窓から、小平蘂岳から三頭山に至る稜線を見たが、前述のピークといい、その隣の釜尻山といい、登高欲をそそる山々である。標高こそ無いが、今後再びこの山域へ足を踏み入れたいと思う。
帰路、最後の二股へ降りる斜面で転倒し、ストックを折ってしまった。最近の山行でシールワックスを塗っていなかったため、湿った雪がシールにくっ付き、高下駄を履いているような状態だった。少し歩いてはストックでスキーの縁を叩いて雪を落としていた。この結果、ストックに細かい傷を付けてしまった。これが些細な力でも簡単にストックが折れてしまった理由である。春先の雪はシールにくっ付くという常識を忘れていたためで、普段からしっか
【参考コースタイム】除雪終了地点9:10
→ .565m 10:26 → 770m休憩地点10:26 → 小平蘂岳 11:50 、〃発11:55
→ 770m休憩地点12:10 、〃発12:30 → .565m 12:57 →
除雪終了地点 13:30
【メンバー】saijyo、チロロ2

主稜線から頂上方向を見る

小平蘂岳頂上へ

小平蘂岳頂上に到着