茂刈山(382 m) ・・・地元旧河北小学校校歌にも歌われた山
|
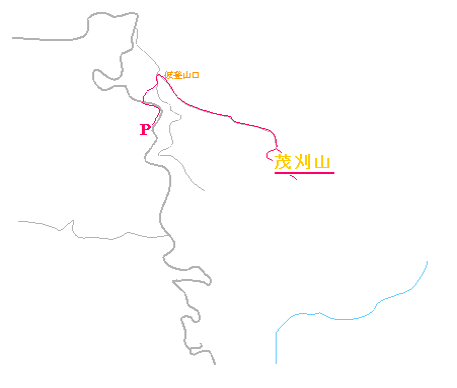 |
1/25000地形図 「桂 岡」
 |
| 仮登山口から少し進んだ地点に車を置く |
 |
| 仮登山口にはしっかり標識がかかっていた (山遊人さん提供) |
 |
| 少々鬱蒼としているが作業道跡を進む |
山遊人さんから誘われて江差町の姥神大神宮渡御祭に行くことになった。札幌に住む私としてはテレビで一度その画像を見た記憶はあるが、エネルギッシュさは北海道らしからぬものがあり、さすがに歴史ある江差の祭りという感じであった。せっかく江差まで行くのだから、どこか山にも登りたいというのが私の本音だった。姥神大神宮渡御祭に参加するまでの時間、どこか軽く一山やってみようとの話となる。山遊人さんが考えていた山と、私が1つの案として持って行った山が茂刈山であった。「一人歩きの北海道山紀行」sakag氏の記録から、仮登山口というのがあって、登山道が刈り分けられているという情報が頭にあったからである。山の高さも低く江差からも近い。しかも登山道であれば少ない時間であっても言うことなしである。
sakag氏のルート図通りに林道を登って行き、「仮登山口」の標識を見る。仮ということもあって、駐車スペースが見当たらず、少し進んだところに車を置く。本当の登山口を作らぬまま人が登らない山になったのだろうか?
そんなこともつい頭に浮かんでしまう。仮登山口から先は8月という時期的なものか、明瞭ではあるが、低い笹が被っている。ダニが活発な6月〜7月は避けたい雰囲気だ。作業道跡を方向を間違えずに進んで行くと分岐となり、斜面を巻くように上流へと向かう作業道跡へ出る。フキや笹等で少し鬱蒼としており、いかにもクマが出てきそうで一人であれば少し心細くなるかもしれない。ただ、踏跡自体は明瞭で、被りがちだが続いている。作業道跡を進んで行くと、そのまま沢形を横断するように終点となる。sakag氏のルートは沢形の右岸側だったが、藪が被っていて刈分けは見当たらなかった。
 |
 |
| 作業道跡終点から藪斜面を登る (山遊人さん提供) | 壊れた頂上標識と金麦 |
終点付近の藪は総じて薄く、ここまで入ればどこからでも登れそうだ。正面の斜面に取り付いてそのまま藪を漕いで尾根上に出る。尾根上の笹薮も割りと薄く、藪が被った登山道といった感じにも見えてくる。頂上が近づくと笹薮は少し濃くなるが、まあこのくらい被っている方が藪山らしくて良い。頂上を覆っている笹は種類が違うのか、密生している割にはすいすい進むことができる。ふと気が付くと頭だけが笹原から飛び出し、視界が大きく広がっていた。道道から見た時に「何だろう?」と思った点は樹木のようで、この付近が最高地点なのだろう。頂上を越えて少し下ったところが草地となっていて、壊れた頂上標識が落ちていた。眺望は素晴らしく、上ノ国町の市街地と海、また、松前半島の山々が広がっていた。当然のことsakag氏の記録で見た小等三角点を探してみたが、背丈ほどの笹薮では見つからない。標高点付近を念入りに捜したがダメだった。
頂上は涼しく心地よい風が吹いており、三角点との撮影用に持ってきた金麦をやっつけて何時になくゆっくりと過ごす。この山を校歌に歌っていた河北小学校は既に廃校、この山での登山会等も今後行われることはないだろう。他の藪山同然に忘れ去られる運命にあるようだ。
下りは沢形から降りてみることにする。こちらはトドマツの植林地となっていて下草はほとんどなくて快適だった。帰路はあっという間に作業道終点となり、後は登って来た作業道をそのまま下って下山となる。ひょっとしたら、ルート的には帰路で使った沢形をそのまま登って行くのが正解だったかもしれない。小さな山であるが、頂上の眺望は素晴らしく、なかなかの山であった。登山道を年に1度でも整備すれば多くの登山愛好者に登られる山となるだろうが、地元にそこまでのエネルギーがあるかどうか・・・
(2016.8.10)
【参考コースタイム】 仮登山口 10:00 → 茂刈山頂上 11:05、〃発 11:55 → 仮登山口 12:35 (登り 1時間5分、下り40分)
【メンバー】 山遊人さん、saijyo、チロロ2、チロロ3(旧姓naga)
… 山行写真 …

仮登山口からしばらくは鬱蒼とした感じ

頂上付近は背の低い笹に覆われている

頂上から見える松前半島の山々

秋の七草の一つカワラナデシコが咲き乱れていた

眼下に上ノ国の市街地が見える