上滝山(1331m)・沙流岳(1422.0m)
|
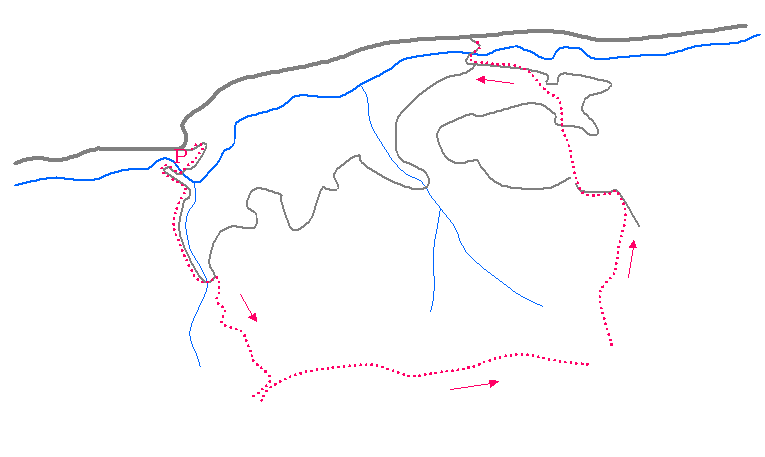 |
1/25000地形図 「沙流岳」
| 沙流岳へ向けて |
| 冬至のため、暗いうちから出発する |
| 上滝山頂上へ |
上滝山と沙流岳は国道275線(樹海ロード)を十勝側へ向かって日勝峠を登って行く途中、6合目付近から見えてくる。上滝山はあまり特徴が無く、地形図なしでは判りづらいが、沙流岳は綺麗な三角錐で一度覚えると多少角度が変っても指呼することが出来る。沙流岳は過去2回、日勝峠から登ったが、今回は反対の西側の稜線から登ってみた。
日勝峠6合目の駐車スペース(林道入口)に車を置く。林道を標高790m付近まで進み、尾根に取付く。この尾根には古い集材路があり、利用出来るだけこれを利用すると効率が良い。(集材路取付きは崩壊しているが、左側の沢を渡って進むと集材路の起点が見つかる。2006.1.14)一部途切れがちではあるが、集材路をつなぐことによって標高1200m位まで楽することが出来る。傾斜が緩くなると進行方向が明るくなり、稜線である。付近の木々は樹氷となっていて、白一色の美しい世界である。上滝山は右側へ進み一登りである。頂上は1331mであるが、三角点は西側の1314.3mのコブにある。この地点の方が樹木も少なく、見晴らしは良いだろうが、我々にとってはこちら(1331m)が本当のピークである。国道側には樹木が繁っていて、あまり見晴らしは利かない。また、楽しみにしていたウエンザル川のダム湖もガスっていて見ることが出来なかった。時間がないので、すぐに沙流岳へ向かうことにする。
途中の1356mピークは巻くことにする。最低コルが1230mなので、これ以下には標高を落とさぬよう南斜面を巻くが、積雪の状態によっては雪崩への注意が必要である(特に1356mピークの南西側が要注意)。わずか100m前後のアップダウンではあるが、この時期は時間との勝負であるため、出来るだけ省エネを意識しなければならない。最低コルから沙流岳ピークまでは標高差約200mの登りである。傾斜は思っていたほどではないが、上滝山の登りで既にエネルギーを使い果たすこともあって、ルート中、一番の厳しい場面である。上部は北西風のためクラストしている。以前に東側の稜線から上った時に2回とも深雪のラッセルであったことを考えると、山行を計画するときには地形だけではなく、尾根の方向による雪の状態も合わせ考えると、より実際的な計画が立てられるのかもしれない。
| 沙流岳周辺のタンネの森 | 沙流岳への登り沙流岳頂上に到着 |
傾斜が緩むと沙流岳頂上である。この時期の天候としては良い方だが、視界はあまり利かず、登ってきた上滝山と日勝峠側が見える程度である。国道を通過する車両の音が僅かに聞こえ、日高にしては人里に近い山なのだと実感する。以前は日勝峠のトンネルの横から入り、1445m峰を目指し、そこから稜線を西進してここに到達した。1445m峰の峠側は良い滑降斜面となっていて、残雪期にはスキーやスノーボードを楽しむ人達で賑わうこともある。
冬型の気圧配置のため西風が強く、寒さのためすぐに沙流岳を後にする。計画では上滝山へ戻ることになっていたが、時間が少ないので北側の尾根を下り直接国道へ出るルートに変更する。.1288mピーク手前のコルを目指し下降するが、頂上直下の斜面はクラストしており、スキーが下手な私としてはここの下降が嫌らしい。東側は雪庇となっている。横滑りと斜滑降で慎重にここを通過する。ピークからコルまでは、雪の状態によっては一番スキーが楽しめるところであろう。
コルからは.1286の東側を巻きぎみに下降する。粉雪が舞う最高の雪質である。次の.1004m手前のコルへ向かう途中で林道と合流し、林道の様子からこのコルを確認、そこからさらに沙流川へ掛かる橋を目指す。
約10〜20分で橋の近くの林道に合流し、橋を渡りすぐに国道へ出る。この付近の沙流川にかかる橋は登路に使った6合目付近の橋と、この奥沙流林道にかかる橋の2ヵ所である。上滝山から沙流岳間で国道側へのエスケープを考える時、この橋を頭に入れて置くと良いだろう。出たところは日勝峠7合目で同6合目まで車の回収に行くが、この間2〜3kmは歩道もなく、大型車両が行き交う幹線道路であり、夜間であれば冬山よりもはるかに危険である。(2002.12.22)
【参考コースタイム】
日勝峠6合目(林道入口)
6:50
→
尾根取付き 7:45 →
上滝山頂上
10:02 、〃発 10:12 →
1230m最低コル
11:00
→ 沙流岳頂上 12:01、〃発
12:06 → 日勝峠7合目(林道出口)
13:53
【メンバー】saijyo、チロロ2